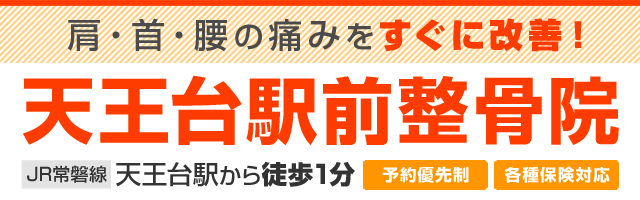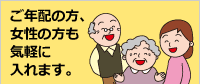巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

肩がこりやすくなっている。
最近寝つきが悪いと感じることがある。
デスクワークや携帯を見ているときに身体が前傾姿勢になりやすくなっている。
最近、頭痛がひどくなっていることがある。
眼精疲労がひどくなっていることがある。
肩こりが起こりやすく、筋肉の過度な緊張や寝違えなどで痛みが生じることがあります。また、首や肩の張りが気になり寝つきが悪くなる場合もあります。さらに、デスクワークや携帯を見ているときに身体が前傾姿勢になりやすく、猫背姿勢やストレートネックの症状が現れることもあります。最近では頭痛がひどくなることや、首回りの筋肉の硬さによって血流が悪くなっている可能性もあります。加えて、首こりによる神経の圧迫で眼精疲労が強くなり、疲れが抜けにくいと感じる方もいらっしゃいます。
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩とは、前かがみの姿勢を続けることで肩が内側に丸まってしまう状態のことをいいます。巻き肩と猫背は似ているようですが、大きな違いは丸くなっている箇所にあります。猫背とは背中が丸まった状態で、背骨に沿って身体の縦のラインが丸くなっています。一方で巻き肩は肩が丸まった状態で、身体の横のラインが丸くなっています。背中は関係がないため、背筋は伸びているのに肩だけ内側に入り込んでいる方も多いです。最初は巻き肩だけだったのに、いつのまにか背中も丸くなり猫背になってしまうケースも多く見られます。
症状の現れ方は?

巻き肩になると肩甲骨が前に出て、腕が内巻きになってしまいます。そうなると、肩こりの原因にもなる僧帽筋という筋肉が常に張った状態になります。また、胸の前の筋肉も硬くなり、その影響でさまざまな症状が現れることがあります。
1.慢性的な首や肩のこり
巻き肩になると肩が本来の正しい位置からずれるため、肩周辺の筋肉の血流が悪くなります。特に肩こりの大きな原因となる僧帽筋が張りやすくなります。
2.疲れやすい
肩が内側に入ることで胸側の筋肉も収縮した状態になります。その結果、前のめりの姿勢となり、頭や首が肩より前に出て頭を支える筋肉に負担がかかります。前傾姿勢になると呼吸時に肺が十分に膨らまず、知らず知らずのうちに浅い呼吸となってしまうことがあります。浅い呼吸は体全体に酸素が行き渡りにくくなり、疲れやすくなる原因のひとつとされています。
3.ボディラインが崩れやすい
肩の位置がずれることで、身体は全身のバランスを保とうと無意識に他の部分をずらそうとします。そのため骨盤の歪みにつながり、お腹やお尻周りが気になったり、脚の長さが変わったり、立ち方が偏るなど外見の変化にもつながることがあります。
その他の原因は?

1.スマートフォンやパソコンの長時間操作
スマートフォンを操作する際は、顔を画面に近づけるため無意識のうちに首が下を向き、肩が丸まって前傾姿勢になりやすくなります。前傾姿勢を続けることで肩が前に出るため、巻き肩になる可能性があります。同様に、デスクワークで長時間パソコンに向かっている方も肩を前に突き出した状態になるため、巻き肩になりやすいといわれています。
2.横向きで寝る
横向きで寝ると、上半身の体重が肩にかかります。そのため無意識に肩の負担を減らそうとして、肩を前にスライドさせて寝てしまうことがあります。これにより肩が前に出てしまうため、横向き寝も巻き肩の原因のひとつと考えられます。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると、以下のような症状が現れることが考えられます。
1.肩こり・首こり
巻き肩によって肩の位置が前にずれると、首と肩を結ぶ筋肉が引っ張られてしまいます。そのため、肩や首の筋肉にこりが生じやすくなります。
2.頭痛
心臓から送られた血液は肩や首を通って脳へ運ばれますが、首や肩の筋肉の緊張によって血管が圧迫されると血流が悪くなってしまいます。その結果、緊張型頭痛が起こりやすくなります。
3.眼精疲労
スマートフォンやパソコンの長時間使用を続けていると、目の疲れや眼精疲労を感じやすくなります。目が疲れていて一晩休めば回復する場合は眼疲労ですが、寝ても疲れや痛みが残る場合は眼精疲労の可能性があります。
4.睡眠の質の低下
巻き肩によって首の筋肉が硬くなると、睡眠の質が低下することがあります。首は自律神経の副交感神経が深く関わっている部分で、身体を休める際に重要な役割を果たしています。しかし、首の筋肉の緊張によって副交感神経が圧迫されると、身体を休める働きが十分に発揮されず、交感神経が優位な状態が続いてしまいます。そのため、睡眠の質が低下しやすくなります。
5.自律神経失調症
巻き肩に伴う首・肩こりや頭痛、睡眠の質の低下などの症状が長期間続くことで、自律神経失調症を引き起こす可能性があります。
以上のような症状が現れる前に、早めの施術や生活習慣の見直しを行うことが大切です。
当院の施術方法について

必要なメニューとしては、肩甲骨はがし、全身矯正、EMS、猫背矯正が挙げられます。
肩甲骨はがしは、肩甲骨周りの筋肉を動かすことが最も大きなメリットだと考えられます。肩甲骨周辺にはインナーマッスルもあり、動かすことで代謝がアップします。そのため体温が上がり、筋肉が冷えにくくなることが期待できます。
全身矯正では、全身の骨格を矯正することで筋肉に無駄な緊張を与えず、すべての筋肉に力を分散させることができます。
また、猫背矯正についても肩甲骨はがしに似た効果が期待できると考えられます。
EMSは、痛みが強い方に対して有効と考えられます。
軽減していく上でのポイント

巻き肩の軽減のための3つの習慣をご紹介します。
1.正しい座り姿勢を意識する
座り姿勢の悪さは巻き肩を悪化させる要因になります。正しい姿勢を維持するために、座るときのポイントを意識しましょう。お尻を背もたれにつけた状態で、頭から背中のラインをまっすぐに伸ばします。天井から糸で吊るされているイメージを持つとよいです。胸が開き、顔が正面を向いていれば正しい姿勢です。
2.スマホ姿勢に注意する
スマホ操作時は、どうしても画面をのぞき込む前傾姿勢になりやすく、これが巻き肩を悪化させる原因となります。肩に負担をかけないために、スマホは胸元ではなく顔付近で持ち、視線を正面にして画面を見るようにしましょう。また、目に負担をかけないために顔から30センチ以上離すことも心がけてください。
3.筋肉を伸ばし、正しい姿勢を維持する
巻き肩になると、胸の奥にあるインナーマッスルが凝り固まり、肩甲骨が前に引っ張られやすくなります。巻き肩の軽減には、姿勢の意識とあわせて簡単なストレッチで筋肉をしっかり伸ばすことが大切です。
監修

天王台駅前整骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:新潟県新潟市
趣味・特技:カラオケ、食べること